どうも、山田店長(@yamada_tencho)です。
よくクレーム対応なんかしてても、お客様自身が言ったりするんですよね。
「お客様は神様だ!」
みたいな事を。
確かに、「お客様は神様」ですよ。
だって、お金くれるんだもん。
そのお金で、私たちはご飯食べられるわけですからね。
そりゃあ、「お客様は神様」ですよ。
でもね、本当のお客様は、
自ら「お客様は神様」だなんて言いませんから。
「お客様は神様」と言うのは、お客様じゃない人が口にする言葉です。
ということで、ここでは、この「お客様は神様です」という、接客業や小売業における魔法の言葉について、深堀りしてみたいと思います。
「お客様は神様です」というその由来や、欧米との違い等、果たしてお客様は本当に神様なのでしょうか?
「お客様は神様です」の由来や起源は?

「お客様は神様です」の由来や起源は?
「お客様は神様です」とは、1961年(昭和36年)頃の自身のステージ上、三波と司会を務めた宮尾たか志との掛け合いMCの中で生まれた言葉である。
宮尾の「三波さんは、お客様をどう思いますか?」の問いかけに、三波は「うーむ、お客様は神様だと思いますね」と応える。
~中略~
ここでの神とは、日本古来の神であるが、三波本人の説明によると、
「舞台に立つときは敬虔な心で神に手を合わせた時と同様に心を昇華しなければ、真実の芸はできない」
「いかに大衆の心を掴む努力をしなければいけないか、お客様をいかに喜ばせなければいけないかを考えていなくてはなりません。お金を払い、楽しみを求めて、ご入場なさるお客様に、その代償を持ち帰っていただかなければならない。」
「お客様は、その意味で、絶対者の集まりなのです。天と地との間に、絶対者と呼べるもの、それは『神』であると私は教えられている。」
と、自身の芸と観客との関係について、自著で述べている。
その後、このフレーズ「お客様は神様です」を流行らせたのは三波の舞台を観たレツゴー三匹である。
-三波春夫wikipediaより
引用が長くなってしまって申し訳ありません。
平成生まれの方はご存じないかもしれませんが、昭和の偉大な演歌歌手三波春夫さんが「お客様は神様です」の起源だったようです。
そう思うと、意外と歴史は浅いと思いませんか?
日本古来からの思想に基づく、商売の理念みたいなイメージでしたが、そうではないようですね。
三波春夫さんの考え方、まさに日本人らしいですね。
芸を披露するという立場ではなく、芸をお客様に見ていただいている。
そう思えばこその、「お客様は神様です」というフレーズだったんですね。
「お客様は神様です」欧米では?

「お客様は神様です」欧米では?
では、欧米ではこの「お客様は神様です」という考え方はどうなんでしょうか?
欧米では、まず文化として、「自由と平等」という考え方が根底にあります。
ここではその解説は割愛させていただきますが、その考えは、歴史がそうさせるのであって、日本人とは歴史の違いがあります。
欧米はこの「自由と平等」という観点から、そもそも「お客様は神様です」などという思考には至りません。
もし、欧米でそんな事を言おうものなら、「じゃあ他所で買えばいいじゃない」となります。
特にアメリカでは、チップという制度があります。
これは、サービスをしてくれてありがとう、という意味が込められています。
つまり、サービスを受ける側がサービスをする側にチップを払うのです。
「お客様は神様です」なんていう国民性だったら、そんなチップを払ったりすることもないでしょう。
とはいえ、
です。
どちらが上とか下とかいう考えはありません。
なので、サービスする側もムダに謝ったりしません。
逆に、欧米では謝罪をするということは、自分に非があったと認める事になってしまいます。
裁判大国なので、そういった言動については非常に敏感です。
そう考えると、日本特有の「お客様は神様です」という考え方は、少し行き過ぎているかもしれませんね。
お客様は神様ではない!

お客様は神様ではない!
日本と欧米との違いはご理解いただけたかと思います。
お客様は、命の次に大事なお金をサービスの対価として支払ってくれます。
だからといって、お金を払ったら何をしてもいいわけではない。
そんな事は分かっているはずなのに、「お客様は神様です」などと言うんです。
大体、「お客様は神様です」というお客様は、お客様ではありません。
サービスを受ける側が、「サービスを受けてやってる」等と思ったら、サービスする側も「サービスをしてやってる」と思うようになります。
こうなると、そもそものサービスの本質が損なわれてしまいます。
客がそこまで考える必要があるのか、と言われれば疑問に思う方もいるとは思いますが、翻って自分がサービスする側になった時の事を考えてほしいものです。
自分がされて欲しい事を相手にもする。
日本の古いことわざにこんなのがあります。
意味は、
「人に親切にすれば、その相手のためになるだけでなく、やがては良い報いとなって自分にもどってくる」
ということ。
つまりサービスとは、お客様のためではなく、自分のためでもあるという事です。
こういった考え方が昔から日本にはあります。
三波春夫さんのように、へりくだってお客様を神様と例えるのも結構ですが、その意味を履き違えている人が多いのも事実です。
お客様は神様ではありません。
それ以上でも、それ以下でもありません。
サービスする側とされる側は、基本的には対等な立場である
これは間違いありません。
でも、やっぱりお客様は神様です

でも、やっぱりお客様は神様です
いろいろ言っておきながらも、実は、「お客様は神様です」。
えっ?さっきと言ってる事違うじゃん!って思われるかもしれませんが、あくまでも「お客様は神様です」というのは考え方の問題です。
さらに言うならば、日本の文化である「謙譲の美徳」だと思っています。
人にお土産を渡す時、「つまらないものですが・・・」と言います。
これは、自分がへりくだって相手を立てる時に使います。
こういった表現は欧米にはありません。
日本古来より伝わる日本の伝統的な考え方です。
サービスする側ではなく、サービスをさせていただく側という考え方も日本特有の考え方です。
この「謙譲の美徳」と言う考え方は、日本人が世界に誇るべき文化です。
そう考えると、やっぱり「お客様は神様です」ということになるのです。
【まとめ】「お客様は神様です」の本当の意味
「サービスされる側ではなく、サービスをしていただく側という考え方」
従業員側は、
「サービスする側ではなく、サービスをさせていただく側という考え方」
この考え方を双方が共有しておくことで、日本の文化であるサービス精神について、最大限のメリットが双方で享受できる。
それが日本の「謙譲の美徳」の利点でもあり、すばらしい文化なのです。
この、日本人の文化を大切にするという気持ち、それこそが日本における接客サービスの基本となるべき根幹の部分なのではないでしょうか?
あなたは店長として、この「謙譲の美徳」、意識されてますか?
関連記事
⇒店長の仕事とは何か?それはトイレ掃除である!と断言します!!
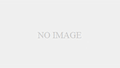

カテゴリー